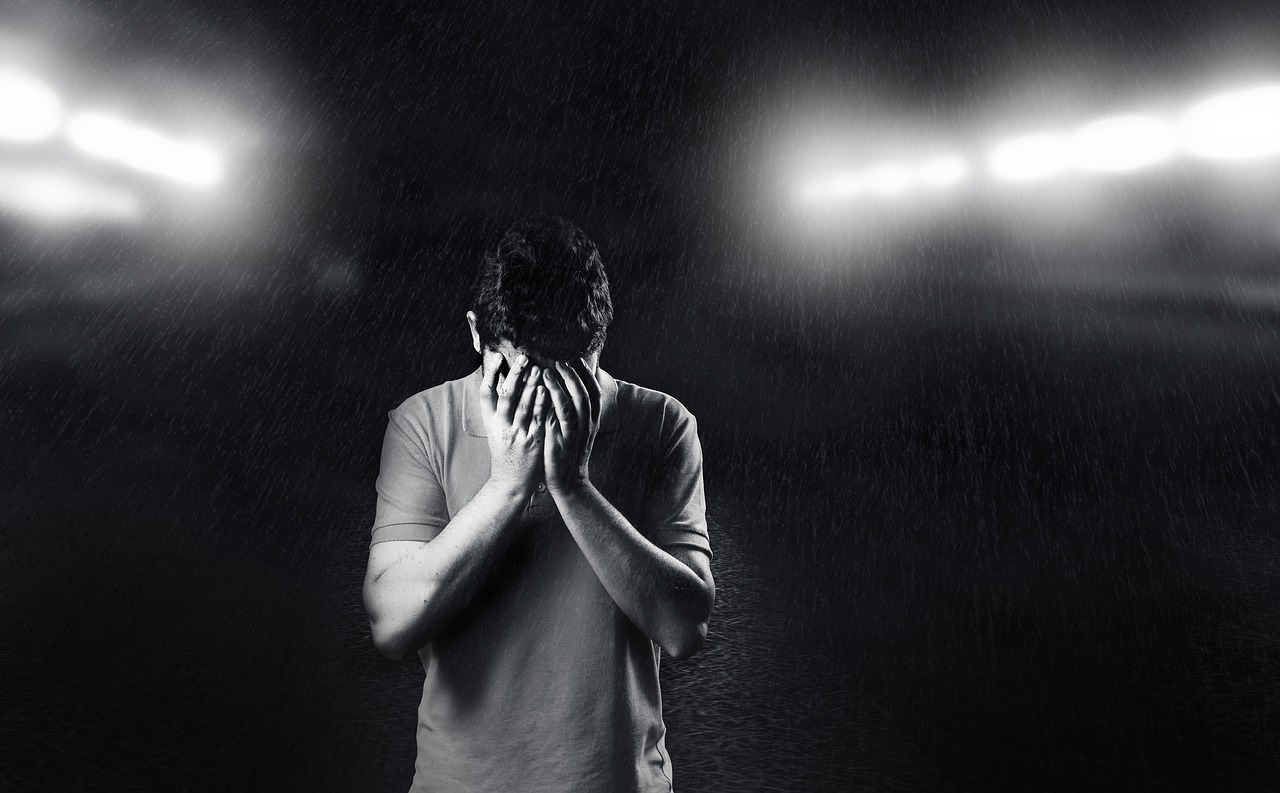ここのところ少しやる気が低下しています。このような時は、自分に気合いを入れる意味でも自己啓発系の本というのは有効だったりします。
本を読んで自分のやる気を奮起したり、今の自分の置かれている状況を振り返ったりするわけですが、それでもそれらの本の全ての内容が受け入れる訳ではありません。
自分として理解できるけど自分にはなかなか難しいなと感じることに「大きな夢や目標を持つ」ということがあります。
よく自己啓発関連の書籍を読むと「人は自分の本当に望んだものなら得ることができる。大きな野望を持てば大きな夢が叶うし、小さなことを望めば小さなことしか叶わない」といいたことが書いてあったりします。
これを読んでうーんとなってしまうのです。
私は子供のころから家庭環境にあまり恵まれなかったのもあって、あまり選択肢がある人生を送ってきたとは言いがたいのです。
学校も特定の公立の学校に行けなければ、進学もできない状況でしたし、就職するときも自分がやりたいことよりも経済的な自律がまず優先でした。ゴール設定が人並みになることだったのです。
結果、マイナスをゼロにすることにはエネルギーは注げるけれど、ゼロの状態から自己実現のためにプラスにもっていくみたいなことが未だに苦手なのです。
今置かれている環境で辛いことがあっても辛抱強く我慢できるけれども、そこが楽しそうであってもレースがしかれていない道を選択できないのです。
だから、もし私が読んだ本のように「人生は自分な望んだ大きさに比例して、得られるものが決まる」のが本当だとすれば、その大きな夢を望む力そのものも私には天賦の能力のように見えます。
すくなくとも大きな志をもっている人は、その情熱で人を巻き込んでいけるから、願い可能性は高くなるかなと。
私にはそういう能力がない。ですが、少なくとも私が読んだ書籍には、それに対する答えは載っていなかったのです。
今週の気になっている本
当ブログでは、割と頻繁に論理的思考には限界があるということを書いていたりするのですが、こちらの本は自分が感じていたことをドンピシャで言い当ててくれています。
人間の理性と感性が衝突したとき、必ず勝利するのは感性です。本書では、それを美を学ぶことにスポット当てて解説してくれています。
今日のアクション
なんか今日のエントリを読むと、私が夢も希望のもない人のように見えそうですが、決してそんなことはなく、ふわっとした夢とか目標とかはいろいろあります。
ただ、ふわっとしていたり、小さなことだったりするのでそこら辺が自己啓発系の人と考えがあわないのです。元気を出すつもりで読んだのですが、かえって考え込んでしまいましたというお話でした。ß
電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。
詳しいプロフィールはこちら。