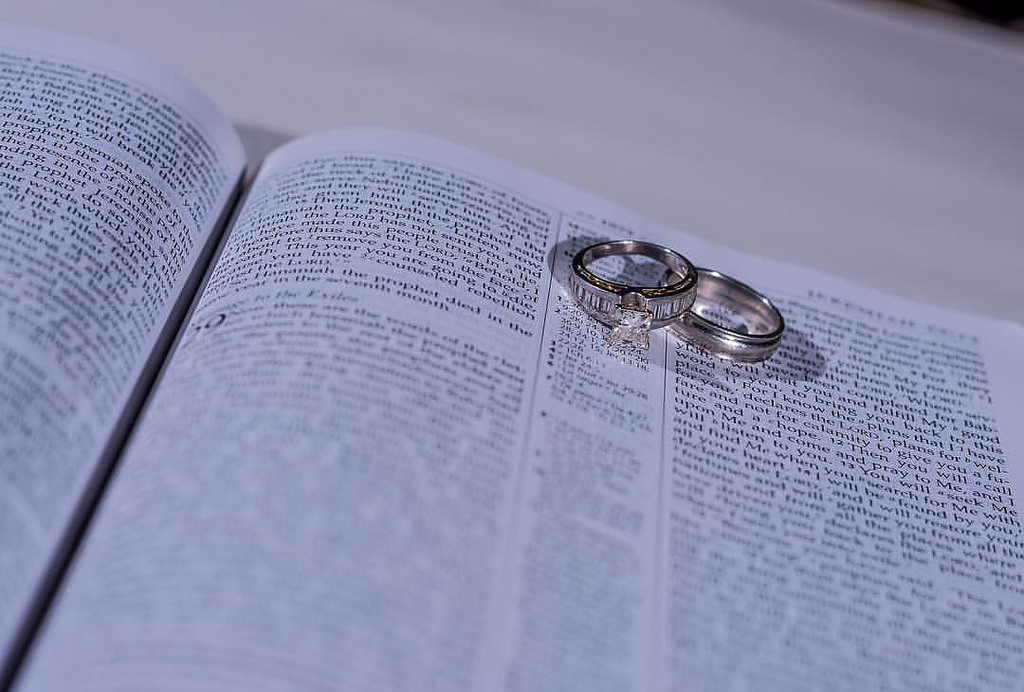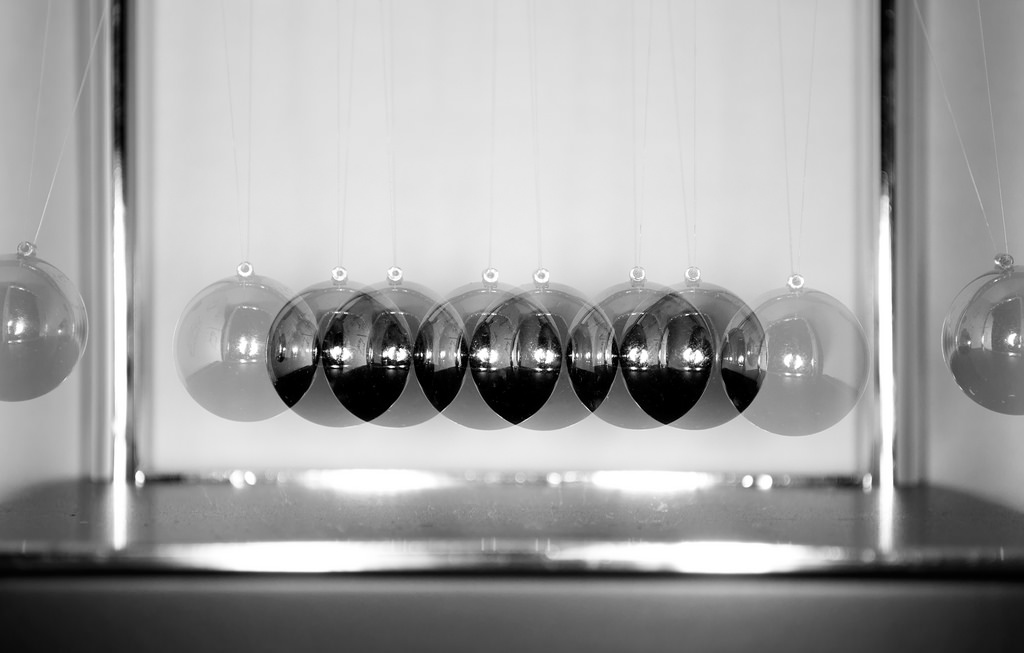2017年も早いもので一ヶ月半が過ぎています。なにかこう最近前にもまして時間が経つのが早く感じることが増えてきました。
実は、これまで自分の人生で中長期的な目標を持って行動したことはほとんどありません。どちらかというとその時の縁やフィーリングを重視して、行動することが私は多いのです。
目標を持ってしまうと、それに縛られてしまう気がしてしまう上、自分出来ないときに自己嫌悪に陥ってしまうからです。
2017年も始まった当初、そのつもりでいました。なんせ年始にこんな記事を書いていたくらいです。
ブログについても、これまでブログを通じてこれを成し遂げたいみたいな明確なゴール設定をしたことはなく、どちらかというと、仕事であったり、プライベートなことであったりの満たされていない部分の気持ちを原動力に書いているようなところがありました。
そして、ブログを書き始めてこれまで、特になにか目標設定をしなくても、ブログを書き続けていると日常生活に面白いことが起こるということを繰り返してきました。イベントを開催できたことも、電子書籍を出したことも明確に最初から目的をやっていた訳ではありません。
ただ、ブログを開始して今年で6年目。毎日に仕事をして、夜に自宅でブログを書くという生活があまりにも当たり前になったためかもしれませんが、「何か新しいことに挑戦したい」という気持ちが沸々を沸いてきています。
今まであまり目標を立てず、淡々と続けるというスタイルを好んできた私にとっては、これは結構大きな心境の変化です。人間、ものごとの感じ方も変わるものなのだと実感しています。
今週の気になっている本
2015年の9月に出版企画コンテストに参加頂いた大杉潤が、このたび商業出版をされることになりました。実は2015年9月のイベントの際にも電子書籍の企画案をプレゼンテーション頂いたのですが、そのときは電子書籍での出版には至りませんでした。
それから約一年半がすぎ、企画をブラッシュアップされて満を持しての商業出版と言えます。もともと大杉さんの企画は電子よりも紙の書籍にフィットする内容だったのですが、根気強く出版までこぎ着けられたはさすがです。
大杉さんは私などをはるかに凌ぐ読書家なので、どんな本が紹介されているかとても楽しみです。
今日のアクション
とはいいつつも、何か具体的にこれがしたいということがあるわけではありません。ただ、新しいことに挑戦したいという意欲だけが沸いてきている状態で、まだまだ空回り気味ではあります。
電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。
詳しいプロフィールはこちら。