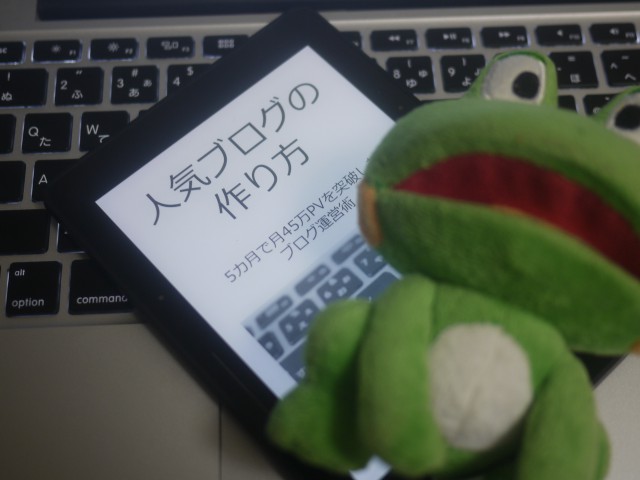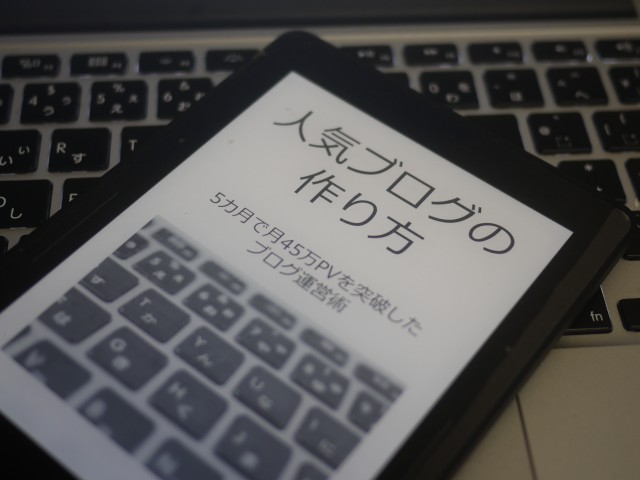先週の6月20日にブログ「No Second Life」の立花岳志さんが主宰される巨大オフ会Dpub11に参加してきました。今回も参加者は約150人で、昼からひたすらに飲んで語らいました。
私はDpub5からの参加で今回で4回目。どちらかというと常連の部類です。
いつもの驚くのはDpubでとなりに居合わせた人に話しかけたら、お世話になっているアプリを作っている人だったり、メジャーなブログを運営している人だったりしている点。
最近は常連になってきているため、昔ほど驚く機会は減りましたが、それでも今回も意外なアプリ開発者の方に会うことができたり、以前から会いたいと考えていたブロガーさんに会うことができました。
こちらは、CLOCK LIFEを運営されている竜さん。

Mr.フリー素材のOZPAさん。

最近、フェルト人形職人といて話題のちゃろさん。

私自身も3年間もコンスタントにDpubに参加し続けていると心境の変化というのはあるものです。
以前と違い自分は自分もイベントを主催する側に回っている点。自分が主催するイベントや提供できるコンテンツがあるので、この人とイベント共催したら面白いんじゃないかとか、新しいことができるんじゃないかという視点が生まれています。
実際、今回のDpubでは一次会で何人かの方には自分が主催している、あるいは運営に関わっているイベントに来てもらえないか相談させて頂きました。
イベントにゲストで来てもらったり、共催したりする相談ってメールとかではなく、対面でしたほうがしやすいです。相手が乗り気でない場合もなんとなくわかりますし。
Dpub中で話したことをきっかけにあらたなプロジェクトがいくつか始動し始めています。今後どんな形になっていくか楽しみです。
こちらは3次会の乾杯の様子。真ん中のいるのはブロガーイベントを主催させたらこの人の奥野さん。

こちらは幹事チームのくらちゃん。盛り上がってます。

今日のアクション
Dpubはただの飲み会なわけですが、人がそこに集まるだけでもらえるエネルギーってあるなぁと実感できるイベントでもあります。
初対面の人とはそんなに深い話をするわけでもないですが、それでも自分の知らない世界のことを知っている人話すだけで新しい発見があったりします。常連で顔見知りの人の中には、自分の新たな道を見つけて進まれている方もいて勇気をもらうことができます。
こうしてブログを続けていられるのも、こういうイベントがあるからと言えます。
主催の立花さん、幹事チームの皆さんありがとうございました。
おすすめ関連エントリ
電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。
詳しいプロフィールはこちら。
![Dpub11に参加してきました。とにかく楽しかった[週記]](https://mon8co.com/wp-content/uploads/2015/06/Dpub11-640x480.jpg)











![らーめん春友祭りに参加してきました[週記]](https://mon8co.com/wp-content/uploads/2015/06/P10308151-640x480.jpg)








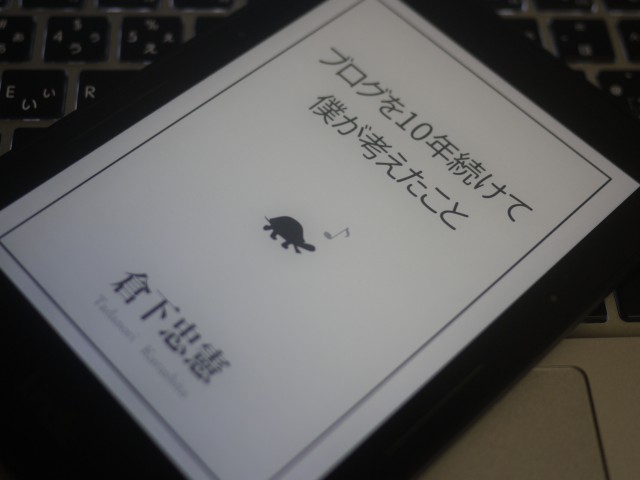

![忠誠心と自立心はどこまで両立するんでしょうか?[週記]](https://mon8co.com/wp-content/uploads/2015/05/3689268230_10acdbc999_b-640x480.jpg)

![言語化すると冷めてしまうという悩み[週記]](https://mon8co.com/wp-content/uploads/2015/05/2233349300_9646c5864e_b-640x480.jpg)